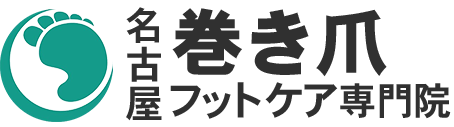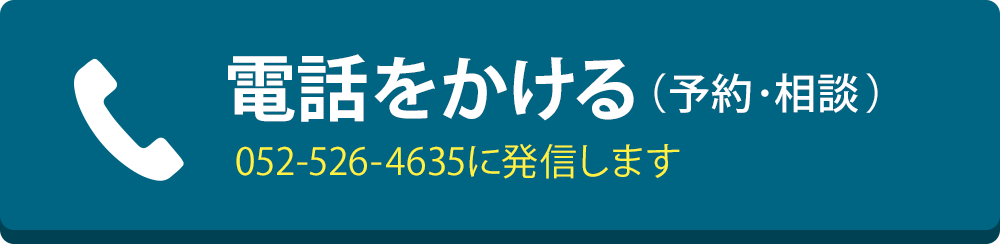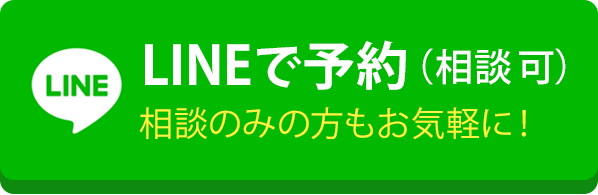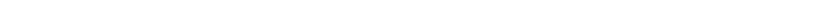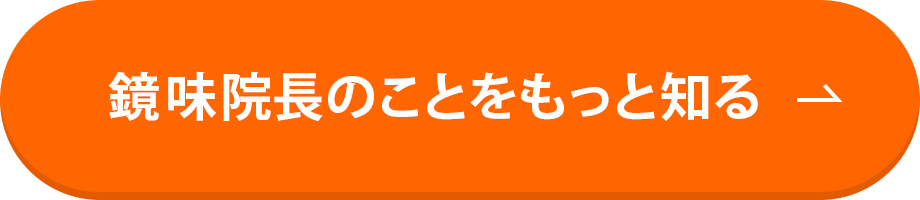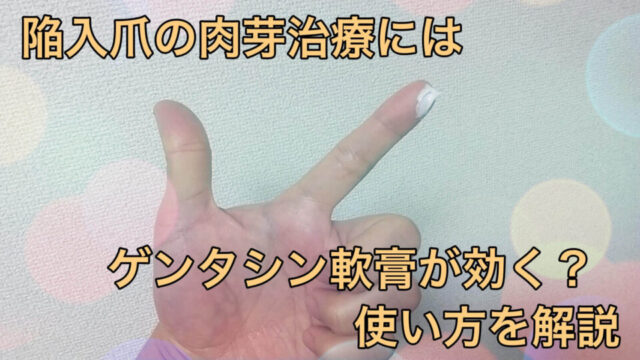
陥入用の肉芽治療後にはゲンタシン軟膏が効く?使い方を解説
あなたは足の爪が皮膚に刺さることで赤くなっていたり、皮膚が盛り上がってしまったり、化膿しているといったようなことでお悩みではないでしょうか?
その場合、陥入爪になっている可能性があります。
陥入爪とは、爪のカドが皮膚に食い込み炎症を起こしている状態です。
この陥入爪を放置すると爪が皮膚に刺さり、傷ついた部分に炎症が生じ雑菌が入ることで感染してしまうと爪の横の皮膚が盛り上がって肉芽(にくげ)と呼ばれる結合組織ができてしまいます。
爪回りに肉芽ができ陥入爪が悪化してしまうと、保存療法で治りにくくなり、手術の適応となってしまう場合もあります。
こちらでは、陥入爪の肉芽治療後に処方されるゲンタシン軟膏の使い方や効果について解説いたします。
陥入爪の手術後に処方されるゲンタシン軟膏
陥入爪は深爪が主な原因となって爪が皮膚に食い込んで傷ができ、傷から雑菌が入って化膿してしまい感染症を引き起こすことがあります。
さらに、傷を放っておくと肉芽と呼ばれる腫瘍ができて爪の周りの組織が腫れてしまうと、爪と皮膚がぶつかりやすくなることで腫れがひどくなり、さらに爪と皮膚がぶつかりやすくなるという悪循環になってしまいます。
爪と皮膚がぶつかる刺激でおこる陥入爪では、感染して化膿した肉芽が痛みをさらに強くしてしまうのです。
陥入爪に対する治療法としては、抗生物質などの保存療法で改善しない場合には、食い込んでいる爪の一部を切除する手術が適応になります。
手術の場合、止血ができていればその日から入浴できますが、陥入爪の手術後にゲンタシン軟膏が処方されます。
ゲンタシン軟膏は雑菌を抑える塗り薬
陥入爪の手術後に処方されるゲンタシン軟膏は、ブドウ球菌やレンサ球菌、大腸菌など多くの雑菌に対して効果があるゲンタマイシン硫酸塩(Gentamicin sulfate)が主な成分で、白色から微黄色の半透明の塗り薬です。
雑菌を抑えるゲンタシン軟膏は、皮膚感染症や潰瘍、やけどなど局所的な治療に使用される医療用医薬品で、抗生物質を含んでいる外用薬です。
ゲンタシン軟膏は雑菌などに対する作用は飲み薬と似ており、塗った部分に局所的な効果があります。
痛み止めと併用する場合も
陥入爪に雑菌の感染を起こした場合には、ゲンタシン軟膏が処方されます。
手術後の痛みと腫れを減らすために、ゲンタシン軟膏とともに、痛み止めも処方される場合もあります。
化膿止めのゲンタシン軟膏を使っても痛みが強い場合には、痛み止めを併用します。
ほとんどの場合は手術前の強い痛みから解放され、手術翌日から普通に歩くことが可能になります。
入浴後の清潔な状態に塗布する
手術した日の入浴は控え、患部を濡らさないようにしましょう。
手術後、包帯を巻いて圧迫して止血できていれば、翌日から入浴が可能になります。
ゲンタシン軟膏は入浴後の皮膚が清潔な状態のときに塗布しましょう。
処方された使用方法を守り、通常であれば、1日1回から数回患部に直接塗布するか、ガーゼなどにのばしたものを患部に貼ります。
抗生物質が含まれているゲンタシン軟膏は、かゆみなどの副作用がでたり、抗生物質が効きにくくなってしまうこともあるので、処方された通りに使用期間や頻度を守って使いましょう。
発疹やかゆみなどの副作用が出たらすぐ相談
保存治療で治らない場合は、最終的に手術を行いますが、手術後にゲンタシン軟膏を使うことで副作用の心配が出てきます。
ゲンタシン軟膏の副作用としては、発疹やかゆみなどがあります。
ゲンタシン軟膏は市販では購入できず、医療機関で処方される医療用医薬品です。
薬を使用して発疹やかゆみなどのアレルギー症状が出たことがある方や妊娠または授乳中、他に薬などを使っている場合は薬の組み合わせによっては副作用の心配もあるので、使う前に必ず主治医に相談しましょう。
発疹、かゆみ、発赤、腫れなどの皮膚の症状がでたら、自己判断で塗るのを止めるのではなく、すぐに主治医または薬剤師に相談しましょう。
まとめ
爪が刺さってできた傷から雑菌が入って感染が起きて炎症が進むと、膿がたまって肉芽ができてしまいます。
病院では陥入爪に対する治療法としてまずは抗生物質などの保存療法から行うことが多いのですが、保存療法をを行っても改善がみられない場合や重度の場合は、食い込んでいる爪の一部や肉芽を切る手術を行います。
手術後には、ゲンタシン軟膏が処方されますが、かゆみや発疹などの副作用がありますので、異常を感じたら我慢せずすぐに主治医に相談しましょう。
陥入爪が悪化して肉芽が形成されてしまうと、強い痛みを伴う可能性が高いです。
そして陥入爪をそのまま放置してしまうと、肉芽はどんどん大きくなってしまい自然に治る確率が減ってしまい意を決して手術をしても再発することもあるので注意が必要です。
陥入爪は爪を深く切りすぎてしまうことが原因で発症することが多く、爪の切り方など生活習慣を見直すことが大切です。
陥入爪が悪化して手術しなくてはいけない状態にならないよう、早めに陥入爪対策を行ったり、専門院に相談することをおすすめいたします。